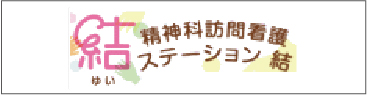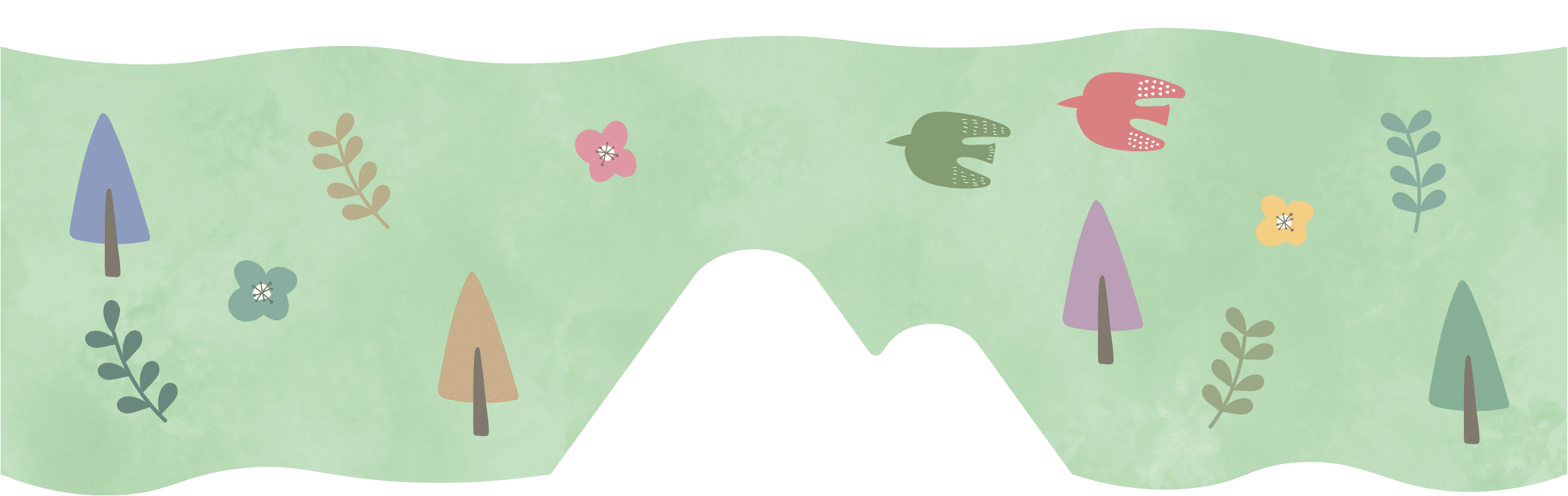
認知症

症状

以下のような症状(周辺症状(BPSD)の悪化等)でお困りになられている方に対して、治療を行っています。
「暴言や暴力が増えてきた」「落ち着かない様子で、昼夜問わず徘徊をするようになった」「『死にたい』等と頻回に発言するようになった」「気分の落ち込みがあり、急に食事を摂らなくなった」「『物を盗られた』など頻回に訴えてくるようになった」「睡眠リズムが崩れて夜に眠れなくなった」「介護拒否があり、嫌がるようになった」等々。
認知症は、単なるもの忘れとは異なり、進行性で日常生活に支障をきたすことが多くあります。早期に治療を開始することで、進行を緩やかにすることはもちろん、お困りごとの解決につながることもあります。
治療法
-
薬物療法
残念ながら認知症の症状を完全に治す薬はありません。薬物療法の役割は、認知症の症状を緩やかにするためのものとなります。
また、精神症状に対しては、非薬物療法(回想法、音楽療法、絵画療法、運動療法、レクリエーション等)が主体となっており、薬物療法は補助的なものとなっています。薬物療法は必要最低限になるように心がけて治療にあたっています。
「薬を飲めば大丈夫」というわけではなく、非薬物療法と組み合わせながら治療を行っていきます。 -
隔離拘束の最小化
入院中やむを得ず、隔離(内側から鍵を開けられない部屋への入室)や拘束(ベッドでの体幹抑制、車椅子の転落防止帯、ミトン手袋等の利用)等の行動制限を行うこともありますが、最終的な手段と考え極力行わないように努めています。
患者様の人権や尊厳に配慮した対応をしています。 -
専門的な援助技術を活用
患者様に対して、心地良い刺激を中心に関わりを持つ「カンフォータブル・ケア」と、楽しく活気に満ちた刺激を提供する「アクティビティ・ケア」の援助技術を用いて、症状の改善を目指しています。
また、多職種で連携を図り、それぞれの専門性を活かしながら症状の早期改善を目指すことはもちろん、ご家族のサポートも行います。
治療・支援の一例
-
1
自宅で、暴言や暴力、徘徊が増えて目を離すことができず対応に困っている。
-
2
当院へ受診相談し、受診予約をとる。
-
3
診察の結果、入院治療が必要とされ入院となる。
-
4
薬物療法、作業療法、心理検査等を実施し入院時の症状が軽快する。
-
5
退院後、自宅での生活が困難なため、公的サービスの調整や関係機関と連携、施設探しを当院が行い、退院をする。
-
6
退院後、外来通院でサポートを継続し、必要に応じ関係機関との連携、公的サービスの調整を行う。
入院のご案内

認知症でお困りの
ご家族へ
家族にできること
WHAT FAMILIES CAN DO
-
本人からのサインに早めに気づく
認知症はちょっとした物忘れから始まることが多いです。「いつもと違う」と早めに気づくことで早期治療につながり、症状を緩和させられることもあります。
もの忘れが始まることで、本人も落ち込んだり、不安になったりすることが多いです。本人の話を傾聴し、訴えに誤りがあったとしても否定せずに受け止めてあげましょう。 -
介護保険等のサービスを利用する
家族のみで認知症の方を支え続けることは困難です。家族で抱え込まず、適切にプロのサービスを利用することで、本人、家族にとっての安心にもつながります。
本人の状況や本人を取り巻く環境に応じて、様々な介護保険等のサービスを組み合わせ活用することができます。 -
家族もしっかり休む
家族にも生活があります。自分自身の時間を大切にしましょう。家族が疲れないことが、認知症の方にとっても安定につながります。
家族がしっかり休めることで、心に余裕が生まれ、本人に対しての温かい対応にもつながります。
ご家族がつながれる
自助グループ
ABOUT SELF-HELP GROUPS
「公益社団法人 認知症の人と家族の会」
https://www.alzheimer.or.jp